2008'07.15.Tue
 | マルコの夢 栗田 有起 集英社 2005-11 売り上げランキング : 95787 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
最近、男性主人公の本ばかり読んでいる。
『犬身』は最初女性だったけど、途中から雄犬になってしまったし。
そろそろ女性が主人公の本も補充するか!というつもりで、確認せずに図書館の本棚から抜いてきたら、これも男性が主人公だった・・・。
(まあ女性作家だから女性が主人公とは限らない訳で、私がアサハカだったんだけど)
それはさておき、よくこの内容とボリュームで、ハードカバー1冊として売り出したなぁ・・・と逆に感心。同じ題材をもっと煮詰めて、濃厚な短編にしたらさぞかし面白かっただろうに。
・・・いや、その短編、川上弘美に書いて欲しいかも。
図書館から借りてきた本の順番により、この次もまた男性主人公の本なのでした。
モテ期フラグかなんかだといいなあ。
-----
<追記>
主人公がお酒に弱くて「コップ1杯で酔っ払うので、燃費がよいと友人にうらやましがられる」という表記があった。
や、お酒が弱いのなんて全然うらやましくないけどなぁ。
飲酒の目的が、「酔っ払いたいから」じゃなくて「美味しいから」だからか。
作者は飲まない人なのかしらん。
PR
2008'07.14.Mon
 | 曲芸師のハンドブック クレイグ・クレヴェンジャー 三川 基好 ヴィレッジブックス 2008-04 売り上げランキング : 200631 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
指が6本あり、数学と文書偽造の天才で、薬の過剰摂取歴を隠すために次々と名前を変えてきた男が、オーバードーズで担ぎ込まれた病院で、自らの頭脳と経験を駆使して精神鑑定士を欺こうとする話。
カウンセリングの会話の合間に、主人公の過去や名前を変えなければいけない事情が挟み込まれる。
そして、アメリカの医療制度、教育制度、刑務所事情の問題も浮き彫りに。
考えようによっては、悲惨な話。
主人公は、家庭環境もよくないし、指の数で苛められ易く、並外れた天才性のせいで特殊学級に入れられたり、犯罪を犯さざるを得ない状況下に陥ったりと、悲劇的な部分が多い。
ただ、そういう状況をめそめそ言い訳にする小説のほうが多い中で、この主人公の、何かのせいにせずに、能力めいっぱい使って生き延びよう、逃げ延びようとするパワーが美しくって。
↑タイトルのセリフを何度も繰り返し、自虐ユーモアは吐いても(解説にもあるように)自己憐憫はなし。
ウソツキの犯罪者を、読んでいる方はどんどん好きになれるのだった。
物語が大きく動いてからは、「この残りページ数でちゃんと終わるのか?」と、左手の中でどんどん残り少なくなるページにはらはら。
そして光が差し込むようなラスト。
面白かったー!
2008'07.11.Fri
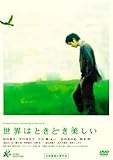 | 世界はときどき美しい 松田龍平.市川実日子.浅見れいな.松田美由紀.柄本明.鈴木慶江, 御法川修 GPミュージアムソフト 2007-08-25 売り上げランキング : 15410 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
キャストに惹かれて借りたのだが、ぼわーんとした綺麗な映像に、自分語りモノローグがかぶさる短編5本オムニバス。
ポエム映画苦手・・・・。
なんだか映像関係の学校の女子が卒業制作に作ったみたいな。
ところでタイトルがジャック・プレヴェール(「天井桟敷の人々」の脚本の人)の「われらの父よ」という詩から取られているそうなのですが、最後にそれが出てくるまで全然気づかなかった。
というのも、私が知っていた訳はこれ↓
「天にましますわれらの父よ そちらにおいでをねがいます
地上は われらがのこりましょう こちらも 時おりすてきです」
で、映画だとたぶんこっちの訳が引用されている↓
「天にまします我らの父よ、天にとどまりたまえ
われらは地上に残ります この世界はときどき美しい」
個人的には前者の方が好きだけれど、タイトルとしては「世界はときどき美しい」の方がびしっとキマるから、後者の方が端正な訳なのかしらん。
こういう訳もあった↓
「天にましますわれらの父よ どうかそこに止まり給え
だが 僕らは地上に止まろう ときにはかくも美しいこの世に」
翻訳って面白くて怖い。
私がこの詩を知ったのは、「たんぽぽクレーター」という小児科専門医療都市が舞台のSFマンガ(復刊してないかなぁと検索していて、「少女漫画でしかありえない特異な牧歌的ハードSF」という評をしてる人を見つけた。深く同意)。
子供がテーマの本には最初の訳がぴったりですね・・・。
まあつまり話題をそらしたくなる程度の映画だったということで。
2008'07.08.Tue
 | サラエボ旅行案内―史上初の戦場都市ガイド FAMA P3 art and enviroment 三修社 1994-11 売り上げランキング : 31564 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
『ノーホエア・マン』を読んだ後、サラエボ包囲について調べていて行き当たった本(↑リンク先に飛ぶと、中身の画像が見られます)。
サラエボ包囲戦の最中に書き留められたもので、カラー写真満載のガイドブックの体裁をとって、戦時下の街の様子をユーモアたっぷりにレポートしている。廃墟、血まみれの路面、死体、燃える車。そんな中の、音楽、舞台、ダンス、結婚、子供たち。
項目は、気候、食事、通貨と物価などの、いかにもガイドブック的なものから、噂、共同墓地、街を出ること、なんていう独特のものまであって、淡々と皮肉に満ちた文章が並んでいる。
ちなみにサッカーの項目は「いつもそうだったように、ここでは外国人チームが負ける」
作り手には、「伝えよう」という意図とは別に、明確に「楽しんでやろう」という意志もあったんだろうと思う。そのたくましさが眩しい。
2008'07.07.Mon
 | 君のためなら千回でも ハリド・アブダラ, ゼキリア・エブラヒミ, ホマユーン・エルシャンディ, アフマド・ハーン・マフムードザダ, マーク・フォスター 角川エンタテインメント 2008-08-22 売り上げランキング : 2323 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
最近行ってないなぁ・・・と思ったので、ふと会社の帰りに。
間に合わなかったもう一本は『ミリキタニの猫』だったので、観賞済みだからOK。
これがまた、アメリカに難民として逃れてきたアフガニスタン人が主人公。
世界は、異国に住まざるを得ない人々で満ちているということの現れですね。
前半は、アメリカで作家デビューした主人公が、祖国アフガニスタンでの少年時代を回想。後半は、少年時代に親友に対して犯した罪を償うために、再び祖国へ渡り、恐怖のタリバン相手に大奮闘(・・・ちょっと違う・・・)。
もうとにかく、アフガニスタンで何があったか、どんな国か、知識もないから、状況を懸命におっかけてあれこれ想像し、アフガニスタンの文化に感心し(お祝いの仕方や、求婚の仕方とか)。
映画としてはかなり長尺で、長過ぎで味が薄まった面もあったけれど、でも「状況を人に知らせる」役割はきちんと果たせていたように思う。
回想シーンでの豊かでのんびりしたアフガニスタンと、後半の同じ地がすっかり荒れ果てた様子のギャップの付け方は上手かった。
クライマックスは、あからさまな御都合主義。それがねえ、もうこれは、わざとなんだろうなと。「ほんとにこういう風になったらいいのにね」っていう願いとか祈りみたいなものなんだろうな、と思わず想像してしまう位、そこに至るまでのあれこれはシビアだった。
ところでこのタイトル(劇中のセリフから)は、あちらの慣用句だったりするのかしら。
-----
映画内で少数民族の少年が差別され、暴行されるシーンがあるせいで、本国では上映禁止。演じた少年たちは暴行を受ける恐れがあるってことで、アメリカに移住せざるを得なくなったとか。
ことによっては真っ向から描くんじゃなく、何か別のやり方があったのかも・・・
・・・・いや、引喩とか暗喩とかは、アメリカ人には通じねえんだよってクローネンバーグも言ってたらしいしな・・・伝えるって難しいな・・・・。
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
プロフィール
HN:
sha
性別:
非公開
アクセス解析
